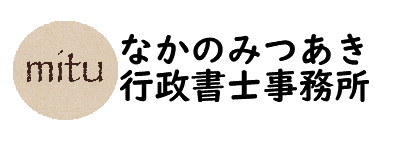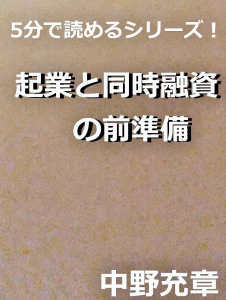遺言
1、遺言の意義は、遺言者が行う意思表示で、その者の死亡によって効力が生じるものをいう。
2、遺言の作成
①意義
遺言の効力は遺言者の死亡時から生じるため(985条1項)、効力発生後にその真意を確かめることはできない。また、他人による偽造・変造のおそれもある。
よって、遺言の作成には、厳格な方式によることが要請され、それにより、遺言者の真意の確保及び紛争の防止を図ろうとしている。
そのため、方式に違反した遺言は効力を生じない。
②普通方式と特別方式
遺言の方式には、普通方式と特別方式がある。(967条)
特別方式による遺言(死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言 976~979条)は、遺言者が普通方式によって遺言することができるようになった時から6か月間生存する場合、その効力を失う。(983条)
これは、特別方式による遺言は、特殊な事情のもとで行われた簡略なものなので、普通方式による遺言が可能になった後にも効力を維持させるべきではないからである。
3、共同遺言の禁止
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない。(975条)たとえ夫婦であっても、共同遺言をすることができない。これは、共同遺言を認めると、自由な撤回をすることができなくなり、遺言者の最終意思を確保することができなくなるからである。
2⃣遺言の方式
1、自筆証書遺言
①自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文が、日付および氏名を自筆し、これを印を押す形式お遺言をいう(968条1項)。
②日付・氏名・押印等
㈠「日付」
日付は特定できるもの(例:Aの70歳の誕生日)であればよい。
自筆証書遺言はの日付として「昭和47年7月吉日」と記載された証書は、日付の記載を欠くものとして無効である。(最判昭和54.5.31)
㈡「押印」
遺言の押印については、指印でもよい。(最判平成1.2.16)
遺言の押印の代わりに花押(署名の代わりに使用される記号・符号)を書くことは、印章による押印と同視することはできず、押印の要件を満たさない(最判平成28.6.3)
押印の習慣がない日本に帰化した外国人については署名も認められる。(最判昭和49.12.24)
㈢数葉にわたる1通の遺言書
自筆証書遺言は、数葉にわたるときでも1通の遺言書として作成されているときは、その火付、署名、捺印は一葉さてていれば足りる。(最判昭和36.6.22)
2、公正証書遺言
①公正証書遺言とは、969条各号が定める方式に従って行われる形式の遺言をいう。(969条)
②公正証書遺言の方式
公正証書遺言の方式は、以下の通りである。(969条)
⑴証人2人以上の立ち合いがあること
⑵遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
⑶公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
⑷遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に変えることができる。
⑸公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3、秘密証書遺言
①秘密証書遺言とは、970条が定める方式に従って行われる形式の遺言をいう。(970条1項)
②秘密証書遺言の方式
秘密証書遺言の方式は、以下の通りである。(970条1項)
⑴遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
⑵遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
⑶遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
⑷公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと
③方式に欠ける秘密証書遺言の効力
秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言として効力を有する。(971条)
④承認及び立会人の欠格事由
以下に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。(974条)
⑴未成年者
⑵推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
⑶公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
5、遺言者の検認
①自筆証書遺言・秘密証書遺言は、検認(遺言についての形式的な検証、証拠保全手続)が必要であるが、公正証書遺言は、検認は不要である。(1004条1項、2項)
②検認の法的性質
検認は、遺言についての形式的な検証、証拠保全手続であり、遺言の内容、効力の有無を判断するものではない(大決大正4.1.16)
3⃣遺言能力
1、15歳に達した者は、遺言能力を有する。(961条)15歳に達すれば、制限行為能力者であっても、単独で有効に遺言をすることができ、保護者の同意は不要である。(962条)
ただし、遺言者は、遺言をする時においてその能力(身分行為上の意思能力)を有しなければならない。(963条)意思能力のない者がした遺言は無効となる。なお遺言は代理によって行うことはできないとされている。
2、成年被後見人の遺言
成年後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時においては遺言をするには、医師2人以上の立会がなければらならない。(973条1項)
4⃣遺言の効力発生時期
1、遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。(985条1項)
2、遺言に停止条件を付した場合
遺言の停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡時に成就したときは、遺言は、条件が、成就した時からその効力を生ずる。(985条2項)例えば、Aが「Bが大学を卒業した時に、Bに全財産を相続させる」旨の遺言をした。
この場合、Bが卒業した後に遺言者Aが死亡したときは、遺言の効力は、遺言者Aが死亡した時(遺言者の死亡の時)から生じる。これに対し、Bが卒業する前に遺言者Aが死亡したときは、その遺言の効力は、Bが卒業した時(条件が成就した時)から生じる。
なお、条件が成就しないことが確定したとき(例:Bが大学を中退したとき)は、無効の遺言となる。
5⃣遺言の撤回
1、遺言の撤回の方式
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。(1022条)遺言を撤回する場合には、その遺言と同一の方式で撤回する必要はない。
例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で撤回することもできる。
2、前の遺言と後の遺言との抵触等
次のいずれかの場合、抵触する部分は、撤回されたものとみなされる。(1023条)
⑴前の遺言が後の遺言と抵触する場合
⑵遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合
3、遺言書又は遺贈の目的物の破棄
遺言者が故意に遺言者を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様である。(1024条)
これは、遺言者が故意に遺言書又は遺贈の目的物を破棄した場合、遺言者に撤回の意思があるものと認められるからである。
なお、遺言者の文面全体に左上から右下にかけて赤色のボールペンで一本の斜線を引く行為は、一般的な意味に照らして、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、「故意に遺言書を破棄したとき」に該当する。(最判平成27.11.20)
4、撤回された遺言の効力
撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときであっても、その行為が詐欺又は強迫による場合を除き、その効力を回復しない。(1025条)これは、遺言者が第1の遺言を復活させる意思をもっていたか否かは不明な場合が多く、復活を望むのであれば、再度、第1の遺言の内容の遺言を作成するべきだからである。
なお、判例は、記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らなときは、当初の遺言の効力が復活するとしている(最判平成9.11.13)
5、遺言の撤回権の放棄の禁止
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(1026条)
例えば、遺言者は、相続人と「この遺言は撤回しない」旨の約束をされられても、その遺言を撤回することができる。
6⃣遺贈
1、遺贈とは、遺言によって遺産の全部又は一部を他に譲与することをいう。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈とがある。特定遺贈とは、具体的に財産を特定した遺贈をいう。(例:「○○に所在する甲土地を贈与する」という場合)包括遺贈とは、抽象的割合で示す遺贈をいう。(例:「財産の2分の1を贈与する」という場合)
2、遺贈に関する胎児の権利能力
胎児は、遺贈については、既に生まれたものとみなされる(965条、886条1項)
3、包括受遺者の権利義務
⑴包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。(990条)
よって、包括受遺者は、遺言者(被相続人)債務も承継し、包括遺贈の承継・放棄は、相続の承認・放棄と同じ手続きで行う。
また、包括遺贈を承認した場合に他に相続人又は包括受遺者がいれば、それらの者と遺産を共有する状態となるが、これを解消するためには、共有物分割手続きではなく、遺産分割手続きによることになる。
⑵包括受遺者と相続人は、次のような点が異なる。
①包括受遺者には遺留分がないが、相続人には遺留分が認められる場合がある。
②包括受遺者には代襲による継承がないが、相続人には代襲による継承が認められ場合がある。
③包括受遺者は法人でもよりが、相続人は自然人でなければならない。
4、遺贈の承継・放棄
⑴受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(986条1項)遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる(986条2項)
包括遺贈の承認・放棄は、相続の承認・放棄と同じ手続きで行うため、民放986条は、特定遺贈のみに適用される。
よって、包括遺贈の場合、遺贈の放棄は、自己のために遺贈の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。(990条、915条1項)
特定遺贈の場合、受遺者は、受遺者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。(986条)
⑵受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
特定遺贈の場合、遺贈の放棄に期間の制限がないため、遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を追う者 例:相続人)やその債権者のような利害関係人は、遺贈の承認又は放棄が確定するまで不安定な立場にたつことになる。
そこで、遺贈義務者その他の利害関係人は、特定遺贈の受遺者に対し、相当の期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができるとされており、受遺者がその期間内遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされる。(987条)
5、受遺者の死亡による遺贈の失効
⑴遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。(994条1項)
停止条件付の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、同様である。ただし、遺言者がその遺言のい別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(994条2項)
⑵代襲による承認の有無
特定遺贈・包括遺贈いずれも、代襲による承継はない。
なお、「Aに対して遺贈するが、Aが死亡した場合にはAの相続人Bに遺贈する」という遺贈は、停止条件付の独立した遺贈であって、代襲による承継ではない。
6、遺贈と死因贈与
遺贈も死因贈与(554条)も、遺言者・贈与者の死亡によって効力を生じるという点で
同じであるか、遺贈が遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は契約であるという違いがある。
よって、遺贈は、受遺者が遺言者に対して承認の意思を表示する必要がないが、死因贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立する。
また、未成年であっても15歳に達した者が、遺贈をするには、法廷代理人の同意を得る必要はないが、未成年が死因贈与をするには、原則として、法廷代理人の同意を得なければならない。
7、「相続させる」遺言
⑴遺言の内容が、特定の遺言を特定の相続人に「相続させる」という趣旨のものである場合、それが遺贈であるのか、遺産分割の方法の指定であるのか明らかであないため問題となる。
判例は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺贈であることが明らかであるかまたは遺贈と解すべき特段の事情のない限り、その遺産は、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに相続により継承されている。(最判平成3.4.19)これは、遺言者の意思は、その遺産をその相続人に単独で相続させようとする趣旨と考えるのが合理的な意思解釈だからである。
例えば、Dが死亡して、相続人はA・Bのみであったが、Dは「相続財産中の甲土地をAに相続させる」旨の遺言をしていた。
この場合、この遺言は、遺産分割の方法の指定にあたり、甲土地を相続人Aに取得させるために、遺産分割の手続きを経る必要はない。
⑵「相続させる」遺言と登記「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については、登記がなくても第3者対抗することができる。(最判平成14.6.10)これは、このような遺言による権利の移転は、法廷相続分の相続の場合と本質的に同じだからである。
7⃣遺言執行者がいる場合の相続人の遺産処分
相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は、遺言執行者がある場合には無効となる。これは、民法1012条1項が「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と規定し、また、民法1013条が「遺言の執行の妨害行為の禁止」を規定しているのは、遺言者の意思を尊重すべきものとし、遺言執行者に遺言の公正な実現を図らせる目的にでたものであるからである。
なお、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為が、遺言執行者として指定された者の就職の承認前にされた場合であっても、「遺言執行者がある場合」にあたるとされ、その行為は無効となる。