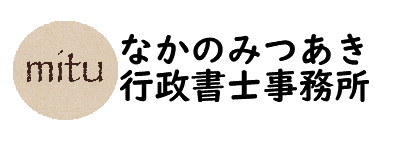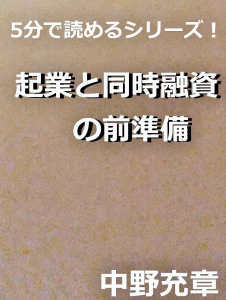相続
相続総論
総説
1、意義
相続とは、ある者(被相続人)が死亡したことにより、その死亡した者の権利義務(遺産)を一定の者(相続人)が受け継ぐことをいう。(882条。896条)
相続人は、被相続の債務を引き継ぐことになるが、債務が多いような時は、「相続の放棄」をすることができる。相続の放棄をしたた者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、権利のみならず、義務(債務)を引き継ぐこともなくなる。(939条)
2、相続の種類
相続には、遺言相続と法定相続がある。
遺言相続とは、被相続人の意思(遺言)による相続をいい、法定相続とは、法律(民法)の規定による相続をいう。
遺言がある場合は二は遺言により相続が行われ、遺言がない場合には民法の規定により相続が行われる。
3、相続分
相続人が複数いる場合(共同相続)、相続財産は、原則として、とりあえず共同相続人全員の共同財産となる。この時の持分割合が相続分である。
4、遺産分割
共同相続の場合、相続財産は、とりあえず共同財産となるが、このままでは不便なので、これを相続人間で、分けることになる。この手続きを遺産分割という。
相続の対象
1、意義
被相続人の権利義務は、被相続人の一身に専属するもの(例:扶養請求権、使用貸借の借主の使用。収益権)を除いて、すべて相続人に継承される。
よって、登記移転義務、代金請求権、引渡債務、取消権、解除権、無権代理人たる地位、建物賃借権(借家権)、善意・悪意たる地位等も継承される。
なお、代理権は、代理人の死亡により消滅するため(111条1項二号)、被相続人が第三者から与えられていた代理権は、相続人に継承されない。
2、相続の一般的効力に関する判例
①占有権は、相続の対象となる。(最判昭和44.10.30)
②生活保護法に基づく保護受給権は、一身専属権であり、相続の対象とならない。(最 大判昭和42.5.24)
③他人の権利の売主を、その権利者が相続し、売主としての履行義務を承継した場合であっても、信義則に反すると認められるような特段の事情のない限り、当該履行義務を拒絶することができる。(最大判昭和49.9.4)
④可分債権・可分債務(例:金銭債務・金銭債権)は、法律上当然分割され、各共同相続
がその相続分に応じて権利・義務を承継する(大決昭和5.12.4、最判昭和29.4.8)。なお、預貯金債権は遺産分割の対象になる(最大判平成28.12.19)
3、相続の対象に関する判例
①身元保証債務・継続的保証債務の承継
通常の保証債務は相続人に承継される。
これに対し、身元保証債務は、特別の事情のない限り承継されない。ただし、相続開始時に、既に具体的に生じていた保証債務は承継される(大判昭和18.9.10)。
また、限度額及び期間の定めのない継続的保証債務は、特段の事情のない限り承継されない(最判昭和37.11.9)。
これらは、契約当事者間の信頼性が特に重視される債務だからである。なお、身元保証とは、雇用契約に関して被用者が使用者に与えた損害賠償債務を身元保証人が保証するものである。
②保険金
受取人を「相続人」と指定している場合の生命保険金・傷害保険の保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となり、相続財産とならない。(最判昭和40.2.2)
③不動産賃借権の保証債務の承継
不動産賃借権の保証債務は相続人に承継される。(大判昭和9.1.30)
④扶養請求権
扶養請求権は一身専属権であるが、具体的に扶養義務の内容が確定し、履行期に達したものは、一般の金銭債務と異ならないことから、相続の対象となる。
⑤連帯債務の相続
連帯債務者の1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。(最判昭和34.6.19)これは、各相続人が全額につき連帯債務を承継するとすると、相続という偶然の事情により債権者に過大な担保を与えることになり妥当でないからである。
⑥金銭
共同相続が生じたとき、相続財産を構成する金額は、相続開始と同時に相続分に従った分割はされず、遺産分割の対象となる。(最判平成4.4.10)これは、金銭が当然に分割されるとしたのでは、遺産分割の際に、金銭を調整に使うことができなくなり不便だからである。
⑦不可分債務の相続
不可分債務を相続した共同相続人は不可分債務を負う。例えば、被相続人が不動産の引渡義務を負う場合において、共同相続人が当該債務を承継したときは、各相続人は不可分債務として不動産の引渡義務を負う(大判昭和10.11.22)
相続人(法定相続人)の確定
1、総説
①意義
相続人は次のように決定される。(887条1項、889条1項、890条)
1、「配偶者」+「子」(配偶者がいたないときは、「子」のみ)
2、子がいないときは、「配偶者」+「直系尊属」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)
なお、直系尊属が複数いる場合は、親等が近い者から相続人になる(父母→祖父母といった順で相続人となる)。
3、子も直系尊属もいないときは、「配偶者」+「兄弟姉妹」(配偶者がいないときは、「兄弟姉妹」のみ)
直系尊属は、1人でも相続権のある子がいる場合には相続人とならず、兄弟姉妹は、1人でも相続権のある子・直系尊属がいる場合には相続人とならない。
よって、次の組み合わせとなることはない。
①「子」+「直系尊属」
②「子」+「兄弟姉妹」
③「直系尊属」+「兄弟姉妹」
4、相続に関する胎児の権利能力
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。(886条1項)
なお、この規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。(886条2項)
5、内縁関係になる者
ア、意義
法律上婚姻していない者(内縁関係にある者)は、ここでいう「配偶者」に含まれず、相続人とならない。
イ、内縁の配偶者の居住権
法律上の夫婦が借家に居住している場合において、夫が死亡したときは、その妻は借家権を相続する。これに対して、内縁者の配偶者の場合は、借家権を相続することができないため、例えば、内縁の夫が死亡した時は、妻の居住が保護されないことになる。
この点、判例は、内縁の妻は、夫の死亡後はその相続人らの賃借権を援用して賃貸人に対し賃借建物に居住する権利を主張することができるが、夫の相続人と並んで当該建物の共同賃借人となるわけではないとしている(最判昭和42.2.21)。
代襲相続
1、意義
代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が、次のいずれかに該当するときにおいて、その者の子(被相続人の孫、おい、めい)がこれを代襲して相続人となる場合の相続をいうこれrこれこれ2、相続人の欠格事由に該当し、その相続権を失ったとき
①廃除によって、その相続権を失ったとき
②「1、相続の開始以前に死亡したとき」
「相続の『開始以前に死亡した』とき」には、被相続人の子等が、被相続人と同時に死亡したとき(同時死亡の推定を受けるときも含む)も含まれる。
なお、「同時死亡の推定」とは、死亡したものが数人いて、いずれが早く死亡したのが判断がついていない場合、これらの者が便宜上同時に死亡したものとして扱うことである(32条の2)
同時死亡者の間では、相続は生じない。また、遺族の効力も生じない。
③相続の放棄
被相続人の子等が、相続の放棄をしたときは、代襲相続は行われない。
④再代襲相続
ア、意義
代襲者(相続人の孫)が、代襲原因に該当するときは、代襲者の子(被相続人のひ孫)が相続人となる。すなわち、代襲相続は、被相続人の子→孫→ひ孫・・・とおこなわれる。(887条3項)
イ、兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹の場合、再代襲相続は行われない(代襲相続は、おい・めいまでしか行われない)。
⑤代襲相続者の存在が要求される時期
代襲相続人となるためには、被相続人の死亡時に、代襲相続人となる資格を有していればよく、代襲原因発生時に有している必要はない。
⑥胎児の代襲相続
胎児についても、代襲相続の規定の適用がある。
⑦養子の直系卑属
ア、縁組前に生まれた場合
「縁組前に生まれた養子の直系卑属」と「養親」の間には、親族関係が生じない。
よって、縁組前に生まれた養子の直系卑属は、養子を代襲して養親の相続人とならない。(887条2項)
イ、縁組前に生まれた場合
「縁組後に生まれた養子の直系卑属」と「養親」の間には、親族関係が生じる。
よって、縁組後の生まれた養子の直系卑属は、養子を代襲して養親の相続人となる。
相続人の欠格事由・指定相続人の廃除
1、相続人の欠格事由
ア、意義
相続人の欠格事由(相続欠格)は、違法行為に対する制裁として、一定の欠格事由がある場合に、法律上当然に当該被相続人に対する相続権を否定するものである。(891条)
なお、すべての相続にかかわる相続能力が否定されるものではない。
欠格事由は、以下のとおりである。
①故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らさせようとしたため、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更をすることを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
イ、対象
相続欠格の対象は、すべての推定相続人である。
ウ、相続資格の回復
相続欠格においては、宥恕’(相続欠格者を許して相続資格を回復させること)についての定めはないが、認められるとされている。
エ、被相続人に遺言書を不当な利益を目的とすることなく偽造した者
被相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の当該行為が相続に関して不当な利益を目的とするものではなかったときは、当該相続人は、「相続に関する被相続の遺言書を偽造し・・・た者」にはあたらない。(最判平成9.1.28)
2、推定相続人の廃除
ア、意義
相続が開始した場合に相続人となるべき者(推定相続人)の廃除は、もっともな理由がある場合に、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所の裁判により当該被相続人に対する相続権を否定するものである(892条)。
イ、請求者
廃除を請求することができるのは、被相続人又はその遺言執行者(遺言で廃除をする場合)であり、推定被相続人が請求することはできない。
ウ、対象
廃除の対象は、遺留分(法定相続人に保障される最低限度の財産分)を有するすいて相続人(兄弟姉妹には遺留分が認められないので、含まれない)のみである。これは、遺留分を有しない推定相続人に相続させないようにするのであれば、廃除によらず、全財産を他の者に贈与又は遺贈(遺言による遺産の全部又は一部の贈与)することによって、目的を達することができるからである。
エ、遺言による推定相続人の廃除
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼっての効力を生ずる。(893条)
オ、推定相続人の廃除の取消し
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。(894条1項)
相続の承認・放棄
1、意義
民法では、相続について選択の自由を保障している。すなわち、相続人は、相続財産を全面的に承継する単純承認(920条)、相続財産の承継を否定する相続の放棄(相続放棄 939条)、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務・遺贈を弁済すべきことを保留して承継する限定承認(922条)、のいずれかを選択することにができる。
なお、相続の放棄をすると、その相続に関しては「初めから相続人とならなかったものとみな」されることから、遺産分割の協議に参加する等する必要がなくなる。(939条)
2、相続の承認又は放棄をすべき期間
ア、意義
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(熟慮機関)。ただしこの期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる(915条1項)
イ、熟慮期間の起算方法
判例は、熟慮期間は相続人ごとに起算されるとしている。(最判昭和51.7.1)
ウ、、相続人が未成年者又は成年被後見人であるとき
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、承認・放棄の熟慮期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算される。(917条)
3、相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
ア、意義
相続の承認・放棄は、一度すると、熟慮期間内でも撤回することができない。(919条1項)
イ、民法総則・親族の規定による取消し
民法総則・親族の規定による取消し(例:制限行為能力者の単独行為、詐欺・強迫による取消し)はすることができる。(919条2項)
この取消権は、追認をすることができるときから6か月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年間を経過したときも、同様である。(919条3項)
これらの規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(919条4項)
ウ、相続放棄についての錯誤による無効の主張
判例は相続放棄について錯誤による無効を主張することもできるとしてる。(最判昭和40.5.27)
4、共同相続人の限定承認
相続人が数人あるときは、限定承認は、相続放棄をした者を除く共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。(923条)
5、方式
ア、限定承認の場合
相続人は、限定承認をしようとするときは、熟慮期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。(924条)
イ、相続放棄の場合
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(938条)
なお、相続開始前に相続を放棄することはできない。
6、相続財産の管理
ア、意義
相続人は、その限定財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りではない。(918条1項)
相続人が承認又は放棄をすることにより、始めた相続財産の帰属が確定するよって、それまでは、相続財産を相続人の固有の財産と混同させないようにすることが必要がある。
そこで、財産の情報を把握できる地位にあり最も適任であるという理由で相続人に管理義務を課す一方で、善管注意義務までも要求するのは妥当でないという理由で規定されている。
イ、限定承認の場合
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。(926条1項)
ウ、相続放棄をしたものによる管理
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。(940条1項)これは、相続人が放棄をすれば、相続財産の管理義務も本来消滅するはずであるが、放棄後すぐに管理を終了すると他の相続人や相続債権者に不都合を生じさせ妥当ではないらである。
7、法定単純承認
ア、意義
法定単純承認とは、一定の事由が生じた場合において、相続人が単純承認をしたものとになすことをいう。(921条)
イ、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(921条1号)
相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純相続したものとみなされる。
ただし、次の行為をしても、単純承認とはみなされない。
①保存行為
②土地は原則として5年、建物は3年、動産は6か月以内の賃貸をすること
ウ、相続人が915条1項の期間何に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき(921条2項)
熟慮期間内に何もしないこと(限定承認又は相続の放棄をしないこと)、単純承認したものとみなされる。
エ、創造人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記憶しなかったとき(921条3項)
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後に、次の行為をしたときは、単純承認とみなされる。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、単純承認とみなされない。
①相続財産の全部又は一部を隠匿したとき
②相続財産の全部又は一部を隠れて又は勝手に消費したとき
③相続財産の全部または一部を悪意で相続財産の目録(限定承認を行う場合に作成するもの)中に記載しなかったとき
相続人の不存在
①意義
相続人のあることが明らかでないと場合、相続財産は法人とみなされ、この相続財産の管理や清算を行うために、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、相続財産管理人を選任する。(951条、952条1項)
なお、家庭裁判所が、相続財産管理人又は、検察官の請求により、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告するが(相続人の捜索の広告 958条)、期間内に相続人としての権利を主張する者があらわれないときは、相続財産は、特別縁故者に分与されるか(958条の3)、国庫に帰属することになる。(959条)
②不在者の財産の管理に関する規定の準用
相続財産管理人は、民法103条に規定する「保存行為」、「利用又は改良を目的とする行為」をする権限を有する。また、これらの権限を超える行為については、家庭裁判所の許可を得て行うことができる。(953条、27から29条)
③特別縁故者に対する相続財産の分与
内縁配偶者に相続権は認めらられない
もっとも、相続人が不存在の場合において、「被相続人と特別の縁故があった者」と認められれば、家庭裁判所は、内縁配偶者に、清算後残存すべき相続財産の全部または1部を与えることができる。これは、相続人が不存在の場合に相続座さんを国庫に帰属させるよりも内縁の配偶者のように相続人だないものの被相続人と特別の縁故関係にあった者に取得させることが望ましいからである。(958条の3第1項、959条)
④共有者の1人が相続人なく死亡した場合
不動産の共有者の1人が死亡し、相続が開始したが、相続人がいない場合、民法255条(共有者の1人が、その持ち分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持ち分は、他の共有者に帰属する)よりも民法958条の3が優先的に適用される。(最判平成1.11.24)
法定相続分
1、配偶者・子が相続人である場合
①意義
配偶者・子が相続人である場合、法定相続分は次の通りとなる(900条1号)。
1、配偶者 2分の1(子の人数に影響されない)
2、子 2分の1(子全体の相続分)
②子が複数いる場合ときは、それぞれの法定相続分は平等となる。(900条4号)
③子の代襲者の相続分は、子が受けるべきであったものと同じである。代襲者が複数いるときは同様に定められる。(901条1項)
2、配偶者・直系尊属が相続人である場合
①意義
配偶者・直系尊属が相続人である場合、法定相続分は次の通りとなる。(900条2号)
1、配偶者 3分の2(直系尊属の人数に影響されない)
2、直系尊属 3分の1(直系尊属全体の相続分)
②直系尊属が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等となる。
3、配偶者・兄弟姉妹が相続人である場合
①意義
配偶者・兄弟姉妹が相続人である場合、法定相続分は次の通りとなる(900条3号)
1、配偶者 4分の3(兄弟姉妹の人数に影響されない)
2、兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹全体の相続分)
②兄弟姉妹が複数いるとき
兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等となる。
ただし、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じである兄弟姉妹の2分の1である。
③兄弟姉妹の代襲者の相続分
兄弟姉妹の代襲者の相続分は、兄弟姉妹が受けるべきであったものと同じである。代襲者が複数いるときは、兄弟姉妹が複数いるときと同様に定められる(901条)
特別受益
1、意義
特別受益制度は、特別受益者(生前贈与や遺贈を受けた相続人)がいる場合において、相続人間の公平を図るために設けられた制度である。
なお、民法903条の「共同相続人」に相続を放棄した者は含まれない。これは、相続を放棄した者は、相続時にさかのぼって相続人とならなかったものとみなされるからである。
(939条)
2、特別受益者の相続分の算定方法
特別受益者の相続分は、次のように算定される(903条1項)。
①「被相続人が相続開始の時において有した財産の価値」+「贈与の価額」(遺贈された財産は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に含まれているので、遺贈の価額を加える必要はない)が相続財産とみなされる。
②①の相続財産をもとに、民法の規定によって各相続人の相続分を算定する。
③特別受益者の相続分は、「②で算定した相続分」-「遺贈又は贈与の価額」となる。
なお、「遺贈又は贈与の価額」が、「②で算定した相続分」以上だと(超過特別受益者がいると)、算定額がゼロ又はマイナスになるが、この場合、超過特別受益者の相続分はゼロとなる(マイナスとなった分を他の相続人がどのように負担するかについては、様々な説・計算方法がある)。
3、特別受益の範囲
特別受益となるのは、次のものである。
①遺贈(目的を問わない)
②婚姻・養子縁組のための贈与(例:持参金、支度金)
③生計の資本としての贈与(例:居住用不動産の贈与)
4、寄与分
1、意義
寄与分制度は、寄与分(相続財産のうち、共同相続人の特別の協力により、維持又は増加した財産)がある場合において、相続人間の公平を図るために設けららた制度である。
2、寄与分が認められた者の相続分の算定方法
寄与分が認められた者の相続分は、次のように算定される(904条の2第1項)。
①「被相続人が相続開始の時おいて有した財産の価額」-「寄与分」が相続財産とみなされる。
なお、寄与分は、協議又は家庭裁判所で定められるが、法的には「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」-「遺贈の価額」が上限となる。
②①の相続財産をもとに、民法の規定によって各相続人の相続分を算定する。
③寄与分が認められた者は相続分は、「②で算定した相続分」+「寄与分」となる。
遺産分割
1、意義 共同相続人は、民法908条の規定により被造族人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、其の協議で、遺産の分割をすることができる(協議分割 907条1項)。
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができる
2、遺産を請求分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分割のほう帆を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。(908条)
「遺産分割の方法」とは、例えば、現物で分ける、競売により換価して価格で分けるというやり方である。
なお、「甲土地をAに相続させる」のような指定も、遺産分割の方法の指定とされている。
3、遺産分割の効力
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。(909条)
4、相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
共同相続人全員によらない遺産分割協議は無効である。
しかし、相続の開始後に認知された相続人は、すでに成立した遺産分割のやり直しを請求することはできず、価額の支払請求権(相続分を金銭で評価した請求権)のみを有する(910条)
なお、相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払いを請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払いを請求したときである(最判平成28.2.26)
5、第三者の分割請求
共同同族人から遺産である不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係を解消するための裁判手続きは、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。(最判昭和50.11.7)
第三者への譲渡によって譲渡部分は遺産分割の対象でなくなること、また、遺産分割審判手続きは、第三者に対し、取得した権利とは何ら関係のない他の遺産を含めた分割手続きの全てに関与したうえでなければ分割を受けることができないという著しい負担をかけること等から、この場合の手続きは、遺産分割でなく、共有物分割となる。
6、分割協議の解除
1、意義
共同相続人は、相続人の1人が他の相続人に対してその協議において負担した債務を履行しないときであっても、遺産分割協議を解除することはできない(最判平成1.2.9)。これは、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後はその協議のにおいてその債務を負担した相続人と、その債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと考えるべきであり、このように考えなければ、遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることなるからである。
2、共同相続人全員の合意による解除
共同相続人は、全員の合意により遺産分割協議を解除することができる(最判平成2.9.27)。これは、法定解除の場合、当事者以外の共同相続人が再分割による不利益エお受ける恐れがあるあるが、合意解除の場合、共同相続人全員が合意しているからである。
7、遺産分割と代償財産
代償財産とは、本体遺産であるにもかかわらず遺産分割時に消失している財産の(消失財産)の代替物として発生する財産のことをいう。
判例は、共同相続人全員の合意により売却された不動産は、遺産分割の対象となる相続財産から逸脱するため、遺産分割の対象にはならないとしている。そして、各相続人は、相続人全員の合意等特段の事情のない限り、その売却代金債権を持分に応じて取得することになるとしている(最判昭和52.9.19)
相続回復請求権
1、相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定して相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものである。
2、請求権者
相続財産の占有を失っている真正相続人である(大判明治38.12.7)
法定相続人は当然に相続回復請求権を行使することができる。
相続回復請求権は一身専属兼であり、その請求をしないで死亡した者の相続人は被相続人の相続回復請求権を承継行使できない(大判大正7.4.9)。
3、権利行使の相手方
表見相続人に限られ、第三取得者は被告適格を有しない(大判大正5.2.8)。
4、権利の行使方法
必ずしも訴えの方法による必要はない。
5、期間制限
相続回復の請求権は、相続人又は法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときの消滅する。(884条)
5年の事項の起算点は、単に相続開始の事実を知るだけでなく、自分が真正相続人であることを知り、しかも自分が相続から除外されていることを知ったときである。(大判明治38.9.19)
相続回復請求権の消滅時効を援用できない表見相続人からの第三取得者(又は抵当権者)は、消滅時効を援用することはできない。(大判昭和4.4.2、最判平成7.12.6)
6、放棄
相続開始前には、相続回復請求権を放棄することはできない。